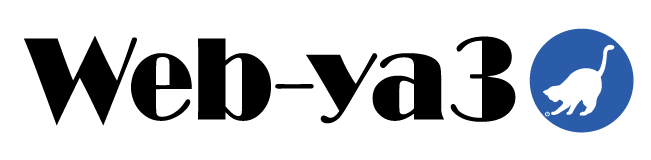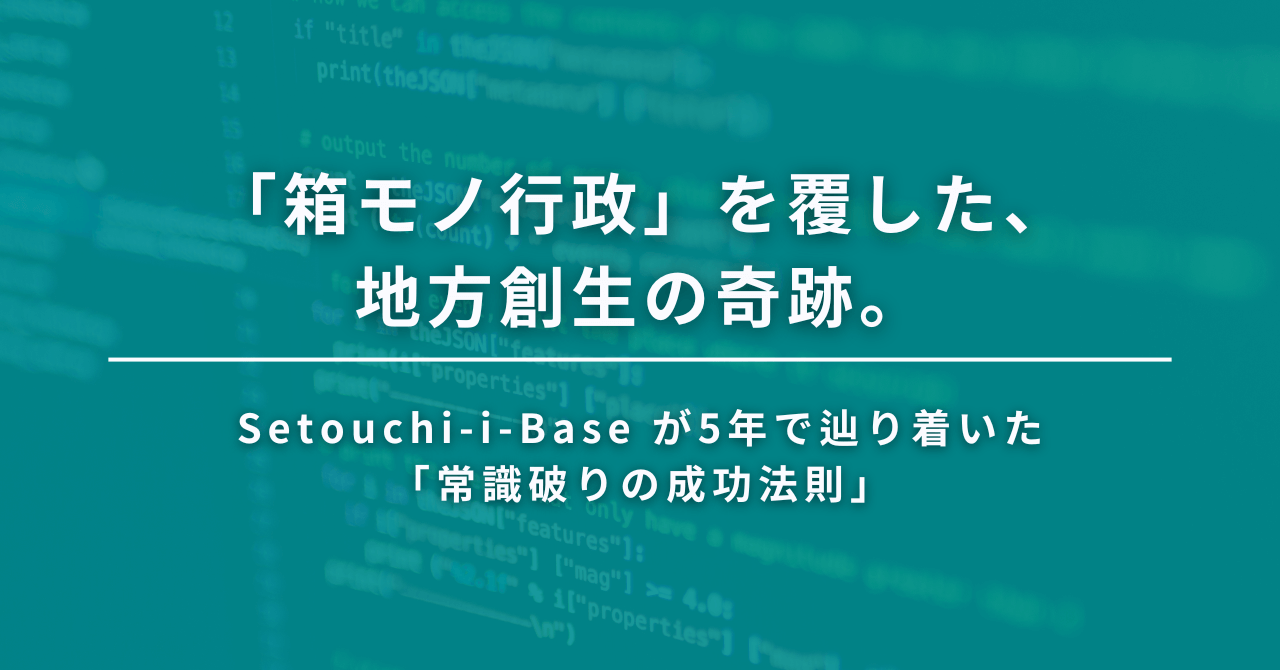今回は、3部構成のトークセッションのうち「第三部:人が育ち、物語が紡がれる拠点」についてまとめています。
イベントの詳細については、Setouchi-i-Base 5周年記念のイベントページをご覧ください。
「箱モノ行政」を覆した、地方創生の奇跡。Setouchi-i-Base が5年で辿り着いた「常識破りの成功法則」
地方における人口減少は、多くの自治体が直面する深刻な課題だ。その対策として巨額の税金を投じて作られた公共施設が、いつしか閑散とし、いわゆる「箱モノ行政」の象徴となってしまうケースは後を絶たない。しかし、そんな常識を覆す例外が存在する。
2020年11月、コロナ禍の真っ只中に香川県で産声を上げたイノベーション拠点「Setouchi-i-Base」は、開設から5年を経て、多くの挑戦者たちを惹きつける活気あるコミュニティへと成長を遂げた。その5周年記念イベントで開催された「元コーディネーター座談会」では、この拠点の成功を支えた初期メンバーたちが集結し、事業計画書には決して書かれない、驚くほど人間臭く、型破りな真実を語った。
この記事では、創設メンバーが明かした、地方創生の常識を覆す「逆説の真理」を解き明かす。
- 池嶋亮さん (株式会社Playable CEO)
Setouchi-i-Baseの立ち上げに香川県に半年間移住。その後、約3年間コーディネーターとしてイベント企画や新規プロジェクト開発などに従事。現在は、大阪梅田のオープンイノベーション施設「Blooming Camp」のコンセプト設計や運営、また地元である松原市観光協会の統括プロデューサーなどを担っている。 - 小西真由さん (株式会社かける小町 代表取締役 )
神戸大学在学中に起業。ケータリングサービスの運営、地域資源を活かした商品開発支援や店舗開発のコンサルティングに携わる。Setouchi-i-Base では 2021〜2024 年 3 月まで事業者の伴走支援、事業成長支援プログラムの企画運営、BoosterGarage の立ち上げと運営に従事。 - 夛田健登さん (馬宿蒸溜所CMO/FM香川パーソナリティ 兼 外部アドバイザー)
香川大学生時代に世界一周を経験し、その後 IT ベンチャーのインターンとして国内外で数十人から 1 万人規模のイベントを企画/運営。馬宿蒸溜所では和三盆ラム酒の製造販売に加え、フリーランスとしてデザイナー、カメラマン、イベンター、ラジオパーソナリティとしても活動中。 2020年~2023年度Setouchi-i-Baseコーディネーター。 - 浅野哲臣さん (香川県政策部デジタル戦略総室デジタル戦略課 課長補佐 )
民間企業を経て、2012年に香川県庁へ入庁。県立病院課を皮切りに、政策課、健康福祉総務課に勤務。政策課在籍時には、地方創生や AI・ドローンなど先端技術の利活用施策に加え、Setouchi-i-Baseの企画・立案に携わる。2023年4月より現職。 - ファシリテーター:山口順子さん(Setouchi-i-Baseコーディネーター)
座談会に登壇したのは、この拠点の設計から現場運営まで、それぞれの立場で深く関わった4名だ。
彼らの証言から浮かび上がってきたのは、「人を育てる」という明確な設計思想と、それを実現するための型破りな実践の数々だった。
すべては「呂律が回らないほどの熱意」から始まった
Setouchi-i-Base の原動力は、人口減少対策という冷静な政策目標だけではなかった。その根底にあったのは、企画立案を担った県職員、浅野哲臣さんの生々しいほどの人間的な情熱である。
特に若者の県外流出という課題を打破するため、県は他の自治体で始まっていた「オープンイノベーション拠点」というモデルに着目した。しかし、浅野さんには強い懸念があった。それは、施設を作って終わりという、いわゆる「箱物行政」に陥ることだ。
この懸念を具体的な行動に変えたのが、浅野さんのむき出しの熱意だった。立ち上げから関わった池嶋さんは、浅野さんとの最初の出会いを振り返る。酒を酌み交わした席で、浅野さんは呂律が回らない状態になりながらも、「何とかしたいんや」という言葉をひたすら繰り返したという。このむき出しの熱意に触れた池嶋さんは、行政の仕様書に見え隠れしていた「箱モノ」の骨格に、この人物の魂をどうやって埋め込むかが自分の仕事だと直感した。
呂律が回らないながらも、ずっと『何とかしたいんや』としか言えない。…まさにおっしゃる『箱物行政』の姿が仕様書に見えていた中で、この箱にどうやって人の魂を彫り込むのかが、僕の仕事だと思ったんです。
無味乾燥なプロセスや形式から生まれる「箱モノ」が魂を宿せないのに対し、理屈を超えた個人の熱意こそが、人を惹きつけ、生命を吹き込む。この熱意から生まれたのが、単なる場所作りではない、人を育てるための「一気通貫の政策」だった。
それは、「学ぶ機会」「実践できるコミュニティ」「仕事につながる支援」という3つの要素が、単に並存するのではなく、有機的に連動する仕組みだ。高度な人材育成講座でスキルを「学び」、そこで得たものを活かせる仲間と「実践」し、コーディネーターによるビジネスマッチングや相談対応によって、挑戦が具体的な「仕事」に結びつく。
「仕事作りって一段上がるんですよね。でもそこを挑戦しないと持続的な価値ある拠点にならないな」と浅野さんが語るように、このプロセスこそが、拠点の持続可能性を支える核心だった。
これこそが、多くの公共事業が見失いがちな、成功への第一法則であり、形式だけの計画主義への明確なアンチテーゼだったのである。
最強の推進力は「半ズボンとサンダルの大学生」だった
次に池嶋さんが打った手は、常識では考えられないものだった。プロジェクトの初期推進力として白羽の矢を立てたのは、当時まだ地元の大学生だった夛田健登さんだったのだ。
これは幸運な抜擢ではなかった。大阪梅田の大規模な都市開発に携わってきた池嶋さんは、街づくりの専門家として、外から来た自分(外からの風)だけではプロジェクトは成功しないと見抜いていた。「香川に外からの風を新しく吹かせれないかな」という思いを持つ「外の風」の存在だけでは不十分だと。地域に根差し、内部から強力な渦を巻き起こす「中でドライブする」存在が不可欠だと考え、数多のプロセスを経て夛田さんに白羽の矢を立てた。
その採用プロセス自体が、既成概念を打ち破るカルチャーを象徴していた。夛田さんへの最初のインタビューは、彼がシェアハウスで寝起きした直後に行われ、さらに彼は、県の職員も同席する初回の公式ミーティングに、半ズボンとサンダル姿で現れたのだ。
初回のミーティングで半ズボンでサンダルできた時は裏で衝撃(が走りました)。『大丈夫か、マジで』って。
この「外の風」と「中の熱」の組み合わせは、単なる役割分担ではなく、化学反応を生む相互作用だった。夛田さんは当時を振り返り、「当時学生だった僕を(大人たちが)尊重してくれた。僕はアイベースの卒業生として育ったんじゃないかな」と語る。外部からの新しい知見や刺激が、地域内部の若者をエンパワーし、主役へと成長させていったのだ。
このエピソードが物語っているのは、Setouchi-i-Base がいかに形式主義を打ち破り、経歴や見た目ではなく、若く熱意ある人材のエネルギーと可能性を信じて権限を委譲したか、ということだ。それは専門家の知見に基づいた、意図的なカルチャー形成だったのである。
実際、初期の拠点は自由で挑戦的な雰囲気に満ちていた。その象徴として夛田さんが語るのが、コーディネーター陣がクリスマスにトナカイなどのコスプレ姿で県の担当者との定例ミーティングに出席したエピソードだ。この逸話は、単なるユニークなカルチャーというだけでなく、行政主導の施設が陥りがちな硬直性を、現場の裁量と遊び心で乗り越えた好例であり、効果的な公民連携における成功の鍵を示唆している。
絶体絶命のコロナ禍が、最高の追い風になった
コミュニティ形成を目的とする施設にとって、コロナ禍の到来は絶体絶命の危機に見えた。しかし、Setouchi-i-Base にとって、この未曾有の制約は最大の好機となった。
対面での活動が一切できなくなったことで、チームはすべての活動をオンラインに移行せざるを得なかった。当時はまだオンラインイベントの「正解」が確立されていなかったため、彼らは何にも縛られることなく、自由な発想で実験を繰り返すことができた。
驚くべきことに、「プログラムもコロナやのに半年で72件回した」という、最初の半年間で実に72本ものオンラインイベントを実施。これにより、オフラインでの活動が不可能な中で圧倒的なスピードで認知度を高め、革新的な拠点としての地位を確立することに成功したのだ。
オンラインの世界ってまだ正解がなかったんで、何やっても許された。だからある意味それはチャンスやったんで、ファーストを取りに行けたっていうのは、タイミングもあってすごく良かったなっていうのがあります。
誰もが手探りだったからこそ、積極的な挑戦が Setouchi-i-Base の名を地域に知らしめる結果となった。大きな制約は、時として組織がそれまで考えもしなかった方法で革新を起こすための、最も強力な触媒となり得る。絶体絶命の状況が、彼らにルールなき荒野を誰よりも早く駆け抜ける自由を与えたのである。
「人を育てる」ことで生まれた、物語とビジネスの成果
拠点としての認知が広がる中、Setouchi-i-Base は次のステージへと進化する。その中心にいたのが、事業成長支援のプロフェッショナルである小西真由さんだ。
小西さんは、利用者の真のニーズを汲み取るため、「YouTubeで番組を作ってまして、ヒアリングを1年間ずっとしてたんですね」と語る。この地道なニーズ調査から生まれたのが、事業成長支援プログラム「ブースターガレージ」だった。これは、事業の成長に本気で取り組む挑戦者たちを継続的に支援する、まさに待望のプログラムだった。
「ブースターガレージ」をはじめとする伴走支援は、目に見える成果を生み出した。小西さんはその手応えを次のように語る。
- 事業の成長
プログラム参加者の中から、事業が成長し、メディア掲載などの成果を出す事例が次々と生まれた - 強固なコミュニティ形成
プログラムの卒業生たちが自主的に集まり、近況報告や悩みを相談し合う文化が醸成。「いい感じでコアができてる」と小西さんが語るように、挑戦者同士の強固なネットワークが生まれた - 周囲への好影響
成功事例が生まれることで、金融機関やメディアからの注目度も高まり、「周りの人もこうなんかいい感じに巻き込」んでいける好循環が生まれ始めている
「人を育てる」という役割は、他の歴代コーディネーターからのメッセージにも共通して見られる。
拠点の役割は場を提供すること以上に、人の可能性を開くことだと実感しました。最初は自信がなかった起業家が自分の言葉でビジョンを語り始め、表情が変わる。その瞬間に立ち会うたび、そう実感しました。
学びを通じて自身のキャリアを見つめ直し、悩みながらも新たな道を切り開いていく事業者の姿に深く心を動かされたことを覚えてます。
Setouchi-i-Baseは、単なるコワーキングスペースやイベント会場から、具体的なビジネス成果と挑戦者のコミュニティを生み出す、まさに「人が育ち、物語が生まれる」場所へと成長を遂げたのである。
成功の鉄則は「共創」より先に「挑戦」を置くこと
座談会の終盤、池嶋さんはコミュニティ運営における洗練された哲学を語った。多くの組織が「共創」や「協業」をスローガンに掲げるが、彼はその順番が決定的に重要だと指摘する。正しい順番は「挑戦して共創する」ことである、と。
彼のロジックによれば、本質的な共創は、まず個々人がそれぞれの「挑戦」に身を投じた後にはじめて生まれる。そして、Setouchi-i-Base の役割とは、まさにその最初の個人による「挑戦」がデフォルトの行動様式となる場所であるべきだと定義した。
今日のタイトルめっちゃいいなと思ったのが『挑戦して共創』なんですよ。で、この順番って逆にする人多いんですけど、絶対逆じゃなくて、挑戦してるから共創ができるっていう。このロジックは多分守っていかないとと思って。
これは、リスクを回避しがちな公共施設のあり方とは真逆の思想だ。真に活気ある協業エコシステムを築くためには、まず個人の野心やリスクテイクを称賛する文化こそが不可欠だという、強力な洞察がここにある。
未来への鍵は、過去の成功を「すべて破壊する」覚悟
5年という節目を迎え、座談会ではそれぞれの立場から未来へのビジョンが語られた。行政の立場から浅野さんは、よりビジネスの成果に繋げ、県外の人々からも「香川に行けば i-Base がある」と認知されるような「地域のシンボル」を目指すと語った。現場で支援を担ってきた小西さんは「ここでやった方がいけてるビジネスを作れる」と評価されるよう、質の高い専門家との繋がりや支援を提供することの重要性を説き、夛田さんはビジネスパーソンの中で「四国といえば、Setouchi-i-Base だよね」という共通認識の確立を目指すべきだと語った。
しかし、最も強烈で、最もラディカルなメッセージを発したのは、立ち上げを牽引した池嶋さんだった。彼は、この施設が本当に価値を持ち続けるためには、過去の成功体験ですら「破壊」するほどの覚悟で、常に自己変革を続けなければならない、という信念を示した。
「この施設自体がチャレンジし続けている状態が最重要」と断言し、「過去の5年の成功もトイレに流して、もう全プログラムを入れ替えるぞぐらい、やっぱチャレンジしないと」と続けた。
彼は、現在行われているすべてのプログラムは入れ替え可能だと考え、さらに究極の失敗の定義としてこう述べた。「10周年の時に、もし自分の名残が少しでも残っていたら、この施設は進化が止まったということであり、終わりだ」と。
逆になんかこう10周年とかに僕呼んでもらった時に、僕の名残とかがあったら多分終わりなんですよ、この施設は。
これは単なる過激な発言ではない。成功体験がイノベーションの最大の阻害要因になりうることを熟知した実践者だからこその警鐘であり、Setouchi-i-Base だけでなく、全国の同様の拠点に対する痛烈なメッセージでもある。
「箱モノ」が過去の決定の静的な記念碑であるのに対し、池嶋さんが描くのは、変化する能力そのものによってアイデンティティが定義される「生きている」組織の姿だ。これは、多くの組織を蝕む官僚的な惰性への究極のアンチテーゼであり、持続可能なイノベーションとは、時に自己破壊的とも言えるほどの、絶え間ない自己改革からしか生まれないことを示している。
未来へ
Setouchi-i-Base の5年間は、行政の強い課題意識から芽吹き、個性豊かなコーディネーターたちが情熱を注ぎ、コロナ禍という土壌でさえも栄養にして、挑戦者を育む唯一無二の拠点へと成長してきた軌跡だった。その成功が建物や予算でなく、人の熱意、常識を疑うカルチャー、そして絶え間ない挑戦の精神によって紡がれる物語であることを、この5年間は雄弁に物語っている。
座談会の最後に、ファシリテーターの山口順子コーディネーターはこう締めくくった。
皆さんの物語を応援する場所、そして物語が交差する場所としても機能していきたい。
あなたの組織やコミュニティには、真のイノベーションを妨げている 常識 や 過去の成功体験 はありますか?
そして、あなた自身の物語を、どこで紡ぎ始めますか?