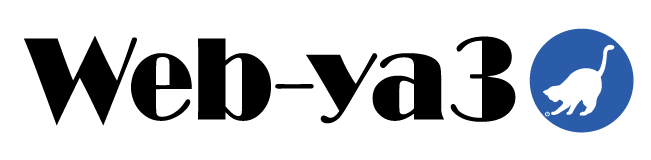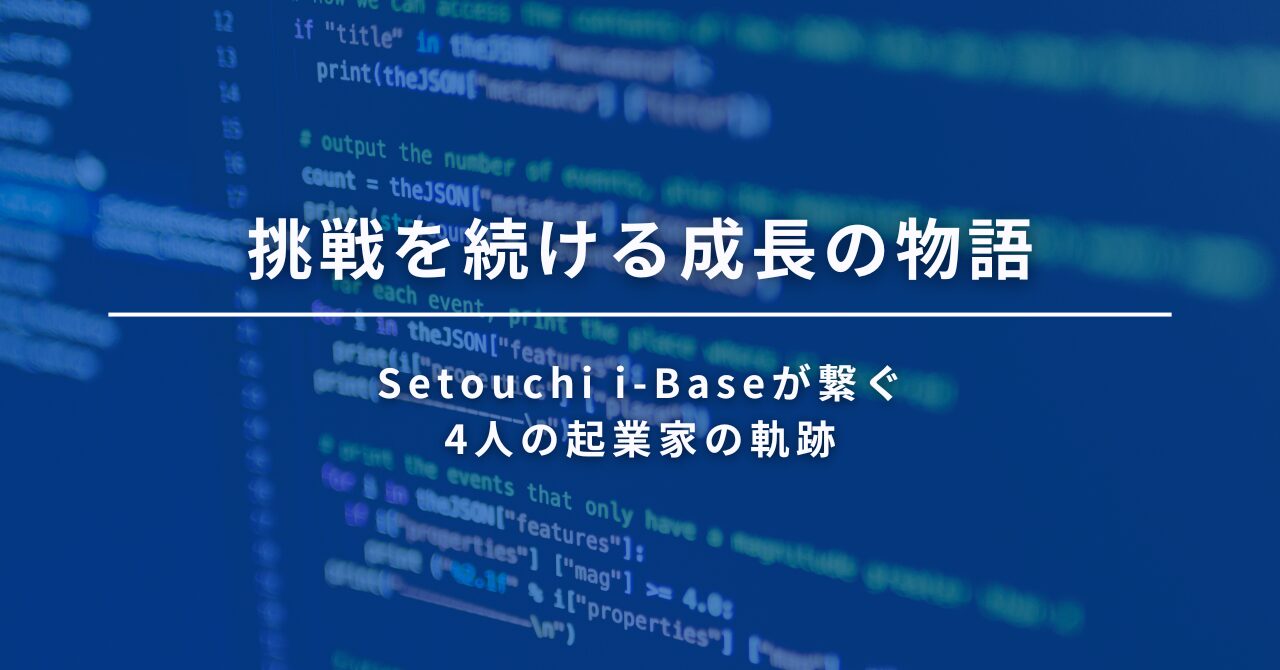今回は、3部構成のトークセッションのうち「第二部:まだ見ぬ挑戦へ ― 成長は物語を続ける」についてまとめています。
イベントの詳細については、Setouchi-i-Base 5周年記念のイベントページをご覧ください。
挑戦を続ける成長の物語 – Setouchi i-Baseが繋ぐ、4人の起業家の軌跡
「Setouchi i-Base」のステージに、4人の起業家が腰を下ろした。鉄工所の伝統を背負う者、ペットとの体験を革新する者、頭の中のアイデアを形にする3Dデザイナー、そしてWebクリエイターとして独立を目指す者。分野も経歴もまったく異なる彼らの口から語られ始めたとき、そこには一本の、力強い共通の糸が見えてきた。
新しい事業を立ち上げる道は、孤独で不安なものだ。しかし、彼らのリアルな対話に耳を澄ますと、その挑戦を加速させ、成長の物語を何倍も豊かにする「場所」の力が浮かび上がる。単なる成功の話ではない成功の裏にあった意外な共通点から、これからの時代を生き抜くためのヒントを探る。
- 植村ちひろさん (有限会社槙塚鉄工所 所属 )
槙塚鉄工所に所属し、製造・販売・広報など幅広い業務を担当。 事業成長支援プログラムBooster Garage2024準グランプリ受賞。 - 大石永津子さん (会社員 )
会社員・2 児の母として働きながら、Webマーケティング×デザインでPR支援を目指し Web デザインを勉強中。Webマーケティング(オンライン講座)、Webクリエイター養成講座 受講。 - 大通龍治さん (オオミチデザインワークス 代表)
オオミチデザインワークスでは3DCADを活用したプロダクトデザインと、オーダーメイドの立体地図イラストを専門としている。Setouchi-i-Baseを拠点に活動中。 - 高崎真希さん・中川 健太郎さん(たびそふと)
「情報の壁を越えて、経験の可能性を広げる」を軸に活動。使いづらさや情報の分散により失われる経験機会の構造的課題を解決したいと考えています。
かがわビジネスアイデアコンテストi-Con 2025 観客賞受賞 - ファシリテーター:中村 宇雄さん(Setouchi-i-Baseコーディネーター)
挑戦の序章、それぞれの事業と原点
本セッションは、背景も事業フェーズも異なる4名が、どのような課題意識や目標を胸に事業へ踏み出したのか、その原点を解き明かすことから始まった。彼らの言葉は、それぞれの挑戦がいかにして始まったかを物語る。
植村ちひろさん(有限会社槙塚鉄工所)
有限会社槙塚鉄工所に所属する植村さんは、建築金物を祖業とする会社で戦略的な転換を担う。フライパンやアウトドア製品など一般消費者向け(BtoC)製品を開発・製造する部署で、ECサイト運営から販売、製造補助までをこなし、BtoB 依存からの脱却という重要課題に取り組んでいる。「皆様の鉄暮らしを支える」というコンセプトのもと、老舗の製造業に BtoC という新たな収益の柱を築こうと奮闘中だ。
高崎真希さん(たびそふと)
「情報の壁を越えて、経験の可能性を広げる」という軸を掲げる高崎さんは、現在、法人化を目指して「たびそふと」の活動を推進している。東京のIT企業に勤務しながらリモートワークや育休期間を活用し、夫の中川健太郎さんと共に事業を準備。情報の非対称性によって失われている「経験の機会」をテクノロジーで取り戻したいという強い思いが、彼女の原動力となっている。
大通龍治さん(オオミチデザインワークス)
「頭の中のアイデアを形にする」ことをミッションとする大通さんは、3D CADを駆使するフリーランスのデザイナーだ。彼の事業の核心は、パンフレットやウェブサイトの平面的なイラストでは伝わりにくい情報を、3D の立体イラストにすることで直感的に表現することにある。クライアントのビジョンやアイデアを、ダイレクトに形にする専門性の高いデザインサービスを展開する。
大石永津子さん(会社員)
会社員として働きながら未来の独立を見据える大石氏。彼女が目指すのは、「デザインとウェブマーケティングを掛け合わせたPR支援」という専門サービスだ。3年前にSetouchi i-BaseのWebクリエイター養成講座を受講したことを機に、現在は勉強や実務経験を通じて着実にスキルを蓄積している。「皆さんよりまだまだ亀の一歩」と謙虚に語りながらも、その視線は明確な目標を捉えている。
これらの全く異なる出発点は、やがて一つの場所に収斂する。Setouchi i-Baseは、彼らにとって単なる「場所」ではなく、成長を促す「触媒」となる。
成長の加速器 Setouchi-i-Base との出会いとその価値
単なるワークスペースに留まらない「Setouchi-i-Base」は、挑戦者のクリティカルな局面で介入し、成長を促すプラットフォームとして機能する。プログラムへの参加、専門家からのフィードバック、そして人と人との繋がり。その価値は、挑戦者のリアルな言葉から浮かび上がってきた。
老舗の弱点を「外の目」で突破する
コロナ禍のキャンプ需要が落ち着き、BtoB 依存からの脱却が急務となっていた槙塚鉄工所。植村さんはその解決策を模索する中で、Setouchi-i-Base の事業成長支援プログラム Booster Garage の参加を決意した。「社内では見えてない我々の弱み」を第三者の視点で洗い出すためだった。
結果は準グランプリ受賞。この受賞は、同社が長年の課題としてきたPR能力の欠如を克服する、決定的な突破口となった。新聞やラジオなどメディア露出が急増し、事業のPR面が劇的に強化されたのだ。
個人の課題感を事業へと昇華させる「加速装置」
高崎さんの挑戦は、愛犬との外出時に感じた「現地に行ったら誰もいなかった」という個人的な課題感から生まれた。このアイデアを事業へと昇華させる「加速装置」となったのが、Setouchi-i-Base のアントレプレナーシップ養成講座であり、そこで勧められたビジネスアイデアコンテスト i-Con だった。
コンテスト出場という目標ができたことで、漠然としていたアイデアは「リアルタイムのドッグラン検索アプリ」という具体的な形へと一気に進展。多くの協力者を得て、アイデアを事業計画とプロトタイプにまで昇華させるプロセスを駆け上がった。
「会社員」のメリットを再現する、フィードバックという生命線
Webクリエイター養成講座から歩み始めた大石さん。彼女は会社員の最大のメリットを「お金をもらいながらフィードバックもらえるっていうところが会社員ってすごいメリット」だと喝破する。フリーランスを目指す上で、このフィードバックという生命線が失われることに強い不安を抱いていた。
その不安を解消したのが、Setouchi-i-Base のコーディネーターとの面談だった。「この方向性で本当に合ってるのかな?」という迷いが生じた際、専門家との対話を通じて客観的な視点を得ることが、次の一歩を踏み出すための羅針盤となった。
「自己分析」と「改善」のサイクルを回す実験場
フリーランスとして活動する大通さんにとって、Setouchi-i-Base は自身の事業を磨き上げるための実験場だ。彼は Setouchi-i-Base での活動を「アウトプットして、その反応インプットして」という、自己分析と改善のサイクルを回す場だと位置づける。練り上げた自己紹介や事業プロフィールを他者に伝え、その反応をフィードバックとして受け取り、さらに磨きをかける。この地道な繰り返しが、事業の輪郭をよりシャープにしていく。
大石さんと大通さんのケースは、Setouchi-i-Base が持つ重要な機能を浮き彫りにする。それは、会社という組織が提供する「フィードバック」や「壁打ち」といった機能を、独立した個人に提供することだ。客観的な視点を得て軌道修正を図る機会は、孤独に陥りがちな個人事業主や独立準備者にとって、事業の成否を分ける極めて重要な価値を持つ。
「人との繋がり」という最大の収穫
i-Con に出場した高崎さんが、最大の収穫として挙げたのは「人との繋がり」だった。コンテスト後もイベントへの参加や事業者紹介を通じて新たなコミュニティが形成され、そこから次の協力関係が生まれている。
このテーマは、植村さんも深く共感する点だ。彼女は「0から1を生み出す難しさ」を乗り越える鍵を、こう語る。
「いろんな人と繋がって、いろんなことを吸収して、自分にとってのプラスになるところをちょっとずつ、ちょっとずつ押し上げていただけるような人と人との繋がり、事業と事業とのつながりっていうのは広げていくのが一番大事なのかな」
この言葉は、分野やステージは違えど、すべての挑戦者に共通する核心的な真理であることを示している。
Setouchi-i-Base が提供するプログラム、フィードバック、そしてコミュニティという機能が三位一体となり、挑戦者たちの成長を加速させたのである。
未来への挑戦、それぞれのネクストステップ
Setouchi-i-Base での経験と学びを踏まえ、登壇者たちはどのような未来を描き、新たな挑戦に向かおうとしているのか。彼らの視線は、確かな手応えと共に、さらにその先へと向けられている。
- 植村さん:会社の魅力発信と、個としての自立
会社の魅力を全国に広げていきたいと力強く語る。同時に、Setouchi-i-Base での学びを通じて個人のスキルアップを継続し、将来的には会社の枠を超え、「職人として、作家として一人立ちする」という大きな目標も視野に入れる。 - 高崎さん:地域密着から世界へ
開発したアプリのユーザー数を増やすため、SNS広報やイベント活動に注力する。犬の飼育率が全国1位である香川県の特性を活かし、地域密着で足場を固めつつ、最終目標として「アメリカ進出」という壮大なビジョンを掲げる。 - 大石さん:着実なステップで目指す専門家への道
「学びの年」を終え、次なるフェーズへと移行する。まずはWebデザイン分野で一つひとつ実績を積み上げ、その先に当初からの目標である「Webマーケティングと掛け合わせたPR支援事業」の実現を見据える。 - 大通さん:自らの未来をクリエイティブする
3D CADという自身の武器が持つ力を信じ、プロダクト制作に留まらない決意を語る。それは、自身のプロダクトだけでなく「自分の未来自体をクリエイティブしていく」という、フリーランスとしての生き方そのものをデザインしていく力強い宣言だ。
4名は企業の成長、グローバル展開、専門家としての独立、そして自己実現と、それぞれのフェーズで明確な次なる目標を掲げている。
共創が生まれる場所の重要性
このパネルディスカッションから浮かび上がった核心は、ファシリテーターの中村さんが指摘した「人が集まる場としての重要性」と、共に創る「共創」の価値に集約される。それは、大企業同士の連携といった壮大なものだけを指すのではない。
4人の物語が明らかにしたのは、むしろ「小さな共創」の積み重ねこそが成長の原動力であるという事実だ。植村さんにとっては、プログラムのメンターとの共創が事業の弱点を克服する鍵だった。高崎さんにとっては、コンテスト後の仲間との共創がコミュニティ形成と次の一歩に繋がった。大石さんにとっては、コーディネーターとの対話という共創がキャリアの方向性を定める羅針盤となり、大通さんにとっては、Setouchi-i-Base の利用者との何気ない会話という共創が事業を磨く砥石となった。
企業の事業転換(植村さん)、ゼロからのスタートアップ創出(高崎さん)、フリーランスとしての事業拡大(大通さん)、そして独立に向けた準備(大石さん)。これらの多様な挑戦のいずれの段階においても、フィードバックを得たり、アイデアの壁打ちをしたり、新たな仲間と出会ったりする「小さな共創」が不可欠であった。
Setouchi-i-Base のようなプラットフォームは、挑戦者たちが集い、互いに刺激を与え、必要な知識や人脈を得て、次のステージへと踏み出すための触媒として機能する。4人の物語が証明したのは、イノベーションは孤独な天才から生まれるのではなく、挑戦者たちが交差し、互いを磨き合う「場」の熱量から生まれるという、地域エコシステムの普遍的な真理であった。